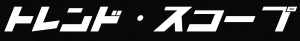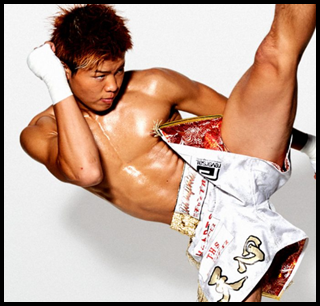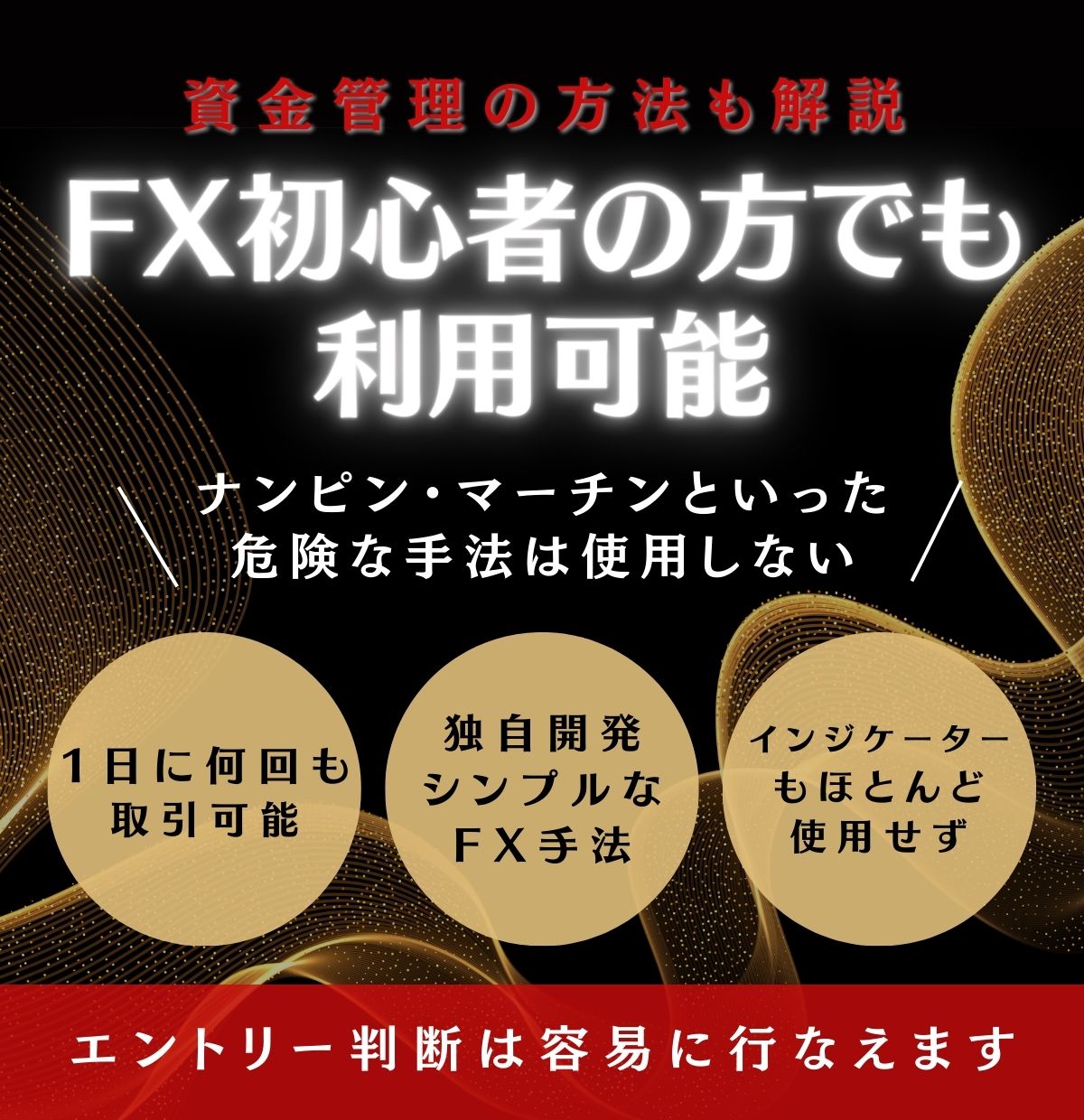1月1日、皇居・宮殿で「新年祝賀の儀」がありました。
「新年祝賀の儀」とは天皇の国事行為のひとつで、毎年元日に開かれているものです。
今回は「新年祝儀の儀」の皇室の衣装について着物など和装でない理由について調べてみました。
元旦に皇居で「新年祝賀の儀」
1月1日、皇居・宮殿で「新年祝賀の儀」がありました。
「新年祝賀の儀」とは、天皇、皇后両陛下が皇族方や三権の長から新年のお祝いを受けられるものです。
天皇、皇后両陛下の他に皇太子さま、秋篠宮ご夫妻ら皇族方、安倍晋三首相や衆参両院議長らも出席しました。
安倍首相らはこの場で天皇、皇后両陛下から新年の挨拶を受けました。
天皇陛下は衆参両院の議長や議員らを前に以下のように語りました。
「衆議院議長、参議院議長をはじめ、一同の祝意に対し深く感謝いたします」
「新しい年をともに祝うことを誠に喜ばしく思います。年頭にあたり、国の発展と国民の幸せを祈ります」
宮殿「松の間」では、皇太子ご夫妻、秋篠宮ご夫妻と長女、眞子さまら皇族方がごあいさつされ、
その後、両陛下が、皇族方とともに宮殿の各部屋を回り、安倍晋三首相や閣僚、衆参両院議長、最高裁長官らから祝賀を受けられました。
同日午後には各国の駐日大使らも宮殿を訪れ、新年の挨拶をされました。
明日2日は「新年一般参賀」があります。
こちらは皇居において、天皇皇后両陛下が国民から祝賀をお受けになる行事です。
毎年テレビで見たことがある光景ですね^^
一般の方を前に天皇陛下が何をお話になるのか、注目したいと思います。
衣装はなぜ着物じゃないの?
1月1日、皇居・宮殿で「新年祝賀の儀」がありました。
この衣装についてネットでは「なぜ着物じゃないの?」という声が上がっています。
確かに、他の国だと国事行司などでは皇族に当たる方は民族衣装を着ているイメージがありますね。
日本の皇族の方は着物などの和服を着ているよりもドレスなど洋装のイメージが強いです。
着物のイメージがあるのは園遊会くらいですね。
まず皇室のルーツをたどると、皇族の方々は元々は公家の代表です。
和服を着るとすると、朝廷や公家の人々が幕末まで着ていたもの、つまり平安装束ということになります。
現代で皇族の方が平安装束を着用するのは皇室のご結婚や、お子様方の着袴の儀くらいです。
平安装束は見た目どおり支度やお手入れも大変で、洋装に比べて経費も格段に高くなります。
また、両陛下が大切にしていらっしゃる皇室のあり方は、
「親しみやすい皇室」「国家財政の負担軽減」「国家の代表としての品位」が上げられています。
陛下や皇族の装束では、正式には挨拶や会釈や会話や手を振ることなどを行ってはいけないものです。
親しみやすい皇室とはかけ離れた衣装というのが分かります。
和服となると平安装束が正装なので、羽織袴を着用するのもふさわしくない‥
和服だと色々難しく面倒な問題が出てくるので、洋装が一番無難ですね^^
洋装は明治維新の影響も?
「新年祝賀の儀」の衣装がなぜ着物じゃないのか、という疑問をさらに深堀りしてみました。
先ほどは皇室のルーツをたどって、皇族の和装=平安装束であることが分かりました。
では、いつ頃から洋装が始まったのか調べてみました。
皇室の洋装化が始まったのは‥明治維新の頃でした。
明治維新の影響で、「洋装令」が出て日本には一気に西洋の文化が入ってきました。
西洋化の波が皇室にも波及し、それからはほとんどの儀式は西洋風にするようになったようです。
国を挙げて西洋文化を取り入れて近代化を進めていく中で、皇室だけが古い文化のままなのはおかしいですからね^^;
明治維新という歴史が現代の皇族の衣装にも影響している事が分かりました。

まとめ
「新年祝賀の儀」の皇族の衣装について、なぜ着物などの和装でないのかについて紹介させていただきました。
皇族のルーツや、明治維新の影響から、現代に合った洋装を選んでいるようです。
ちなみに女性皇族の服装の基本を決めるのは皇后陛下で皇后→皇太子妃→宮妃の順で服装が決まっています。
なので色が被ったりすることがないようになっているのですね^^